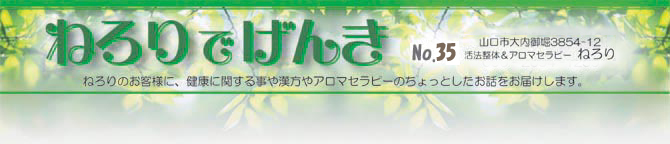
 ■東洋医学では冬と一番関わりの深い内臓の気を『腎』としています。この『腎』というのは、すごく広い意味があって、尿などの水の調整はもちろんのこと、生殖器などその人の活力全体までも含んでしまいます。そして、この活力の源としての『腎』の不調と深い関係の表情を「恐れる、驚く」としています。「恐れ」はお化け屋敷などで一時的に感じる場合もありますが、身体に不調を及ぼす時は、もっと強い「恐れ」や慢性的な「恐れ」です。「恐れる」という時は、何か具体的なことの場合ですので、漠然としている時は「不安」と言ったほうがいいかもしれません。「不安」というのは、怖い物がはっきりしていないので、対応が難しく厄介なものです。今回はこの厄介な「不安」について書いてみました。
■東洋医学では冬と一番関わりの深い内臓の気を『腎』としています。この『腎』というのは、すごく広い意味があって、尿などの水の調整はもちろんのこと、生殖器などその人の活力全体までも含んでしまいます。そして、この活力の源としての『腎』の不調と深い関係の表情を「恐れる、驚く」としています。「恐れ」はお化け屋敷などで一時的に感じる場合もありますが、身体に不調を及ぼす時は、もっと強い「恐れ」や慢性的な「恐れ」です。「恐れる」という時は、何か具体的なことの場合ですので、漠然としている時は「不安」と言ったほうがいいかもしれません。「不安」というのは、怖い物がはっきりしていないので、対応が難しく厄介なものです。今回はこの厄介な「不安」について書いてみました。
 ■不安な時の身体の状態は、交感神経が優位な状態ですので、呼吸が速く浅くなりがちです。その状態がしばらく続くと、身体の隅々まで充分に酸素が行き渡りにくくなりますから、身体がだるくなったり、集中力が落ちたりします。また、胃腸の働きも落ちますので、便秘や下痢などの症状も出る場合があります。身体に不調が起きると気持ちがますます落ち込むので、不安がより強くなってしまいます。この悪循環から、どこかで抜けなければなりませんね。不安の原因がわかっていて、対処可能なものであれば良いのですが……それが出来ないから、不安なのですよね。
■不安な時の身体の状態は、交感神経が優位な状態ですので、呼吸が速く浅くなりがちです。その状態がしばらく続くと、身体の隅々まで充分に酸素が行き渡りにくくなりますから、身体がだるくなったり、集中力が落ちたりします。また、胃腸の働きも落ちますので、便秘や下痢などの症状も出る場合があります。身体に不調が起きると気持ちがますます落ち込むので、不安がより強くなってしまいます。この悪循環から、どこかで抜けなければなりませんね。不安の原因がわかっていて、対処可能なものであれば良いのですが……それが出来ないから、不安なのですよね。
 ■不安を消し去るというのは、難しいかもしれませんが、一時的でも忘れる、または軽くしていくというのは可能だと思います。その方法を考えてみましょう。
■不安を消し去るというのは、難しいかもしれませんが、一時的でも忘れる、または軽くしていくというのは可能だと思います。その方法を考えてみましょう。■まず、不安はストレスの一つですのでストレスに対応できるホルモンの分泌をよくしましょう。 近年「幸せホルモン」と言われるほど、良い気分に影響を与えるセロトニンの分泌をよくしましょう。
 セロトニンは、不安を抑えるだけでなく痛みを和らげる働きがありますし、睡眠ホルモンのメラトニンの元でもあります。それから「行動すること」と関係が深い「快感ホルモン」ドーパミンも大切です。不安を解消するためには、何か楽しいことをして気持ちを紛らわすと良いですが、そうは言っても、せっかく頑張って何か行動をしても「楽しい」と感じなければ続かなしい、逆にしんどくなったりします。やる気にはセロトニンも深く関係していますが、「気持ち良い」「楽しい」と感じるにはドーパミンが重要です。なお、ドーパミンは過度に分泌されると問題行動を起こす事がありますが、セロトニンはドーパミンを調整する力も持っています。
セロトニンは、不安を抑えるだけでなく痛みを和らげる働きがありますし、睡眠ホルモンのメラトニンの元でもあります。それから「行動すること」と関係が深い「快感ホルモン」ドーパミンも大切です。不安を解消するためには、何か楽しいことをして気持ちを紛らわすと良いですが、そうは言っても、せっかく頑張って何か行動をしても「楽しい」と感じなければ続かなしい、逆にしんどくなったりします。やる気にはセロトニンも深く関係していますが、「気持ち良い」「楽しい」と感じるにはドーパミンが重要です。なお、ドーパミンは過度に分泌されると問題行動を起こす事がありますが、セロトニンはドーパミンを調整する力も持っています。
■セロトニンの量を増やすには、目覚めた時に屋内で良いので朝日を浴びるようにしましょう。ラジオ体操やウォーキングなど身体のリズムがとれる運動も分泌を促します。
 ■セロトニンやドーパミンの材料を摂るためにお食事も大切です。これらの元になるアミノ酸・トリプトファンをしっかり食べましょう。大豆食品やお肉や魚などの動物性タンパク質に多く含まれています。これらは、前号で書いた神経の安定に不可欠なビタミンB群を多く含んでいるものも多いです。その他、ビタミンCや亜鉛・鉄・カルシウムなどのミネラルも心の安定に役立ちます。でも良いからと言って肉などタンパク質ばかり食べていると違う不調がおきますので、不安が大きい時ほど、魚・肉・野菜とバランスの良い食事を心がけてみましょう。御飯やお菓子などの炭水化物には、トリプトファンの吸収を高める働きがあるようですので、適度に食べましょう。
■セロトニンやドーパミンの材料を摂るためにお食事も大切です。これらの元になるアミノ酸・トリプトファンをしっかり食べましょう。大豆食品やお肉や魚などの動物性タンパク質に多く含まれています。これらは、前号で書いた神経の安定に不可欠なビタミンB群を多く含んでいるものも多いです。その他、ビタミンCや亜鉛・鉄・カルシウムなどのミネラルも心の安定に役立ちます。でも良いからと言って肉などタンパク質ばかり食べていると違う不調がおきますので、不安が大きい時ほど、魚・肉・野菜とバランスの良い食事を心がけてみましょう。御飯やお菓子などの炭水化物には、トリプトファンの吸収を高める働きがあるようですので、適度に食べましょう。
■少量のお酒はこれらのホルモンの分泌を促してくれますので、軽い不安の時は良いかもしれませんが、過度になると醒めた時に不安が強くなることがありますし、毎日の量が増えていくと問題が起きるので要注意です。
 ■また、不安な気持ちを書き出したり、誰かに話してみましょう。誰かに話す時には一緒に落ち込んでしまう人や反論してくる人ではなく、受け止めてくれる人が良いです。身近な人に話すと気を遣ってしまい充分話せないという方は、関係のない第三者の方が意外と話しやすいかもしれません。(ねろりでも遠慮無くどうぞ)話したり書いたりすることで、ゴチャゴチャの頭の中が少しは整理されるかもしれませんよ。もしかして、不安の中には対処ができる事があるかもしれません。不安が大きい時は決して一人で抱え込まないで下さい。セロトニンの量はお薬でも調整出来ますので、不安がひどい場合は心療内科などに受診して、少しでも早めに対処して下さい。
■また、不安な気持ちを書き出したり、誰かに話してみましょう。誰かに話す時には一緒に落ち込んでしまう人や反論してくる人ではなく、受け止めてくれる人が良いです。身近な人に話すと気を遣ってしまい充分話せないという方は、関係のない第三者の方が意外と話しやすいかもしれません。(ねろりでも遠慮無くどうぞ)話したり書いたりすることで、ゴチャゴチャの頭の中が少しは整理されるかもしれませんよ。もしかして、不安の中には対処ができる事があるかもしれません。不安が大きい時は決して一人で抱え込まないで下さい。セロトニンの量はお薬でも調整出来ますので、不安がひどい場合は心療内科などに受診して、少しでも早めに対処して下さい。 ■寒い冬がやってきましたが、寒いということは身体にとって悪いことばかりではないようです。冬眠しない動物にとっては一番痩せやすい季節のようで、秋に蓄えた脂肪を燃やす季節でもあります。ねろりの警備員・やせポッチ犬は、少しでも寒いと身体を震わせ熱を作り出しているので、冬場はいくら食べてもやせポッチのままです。夏場は冬場の半分程度しか食べませんが、痩せません(これ以上痩せたら骨になるかも……)。
■寒い冬がやってきましたが、寒いということは身体にとって悪いことばかりではないようです。冬眠しない動物にとっては一番痩せやすい季節のようで、秋に蓄えた脂肪を燃やす季節でもあります。ねろりの警備員・やせポッチ犬は、少しでも寒いと身体を震わせ熱を作り出しているので、冬場はいくら食べてもやせポッチのままです。夏場は冬場の半分程度しか食べませんが、痩せません(これ以上痩せたら骨になるかも……)。 ■ワンコも人間も、食べた物をお腹の中でエネルギーに利用できる形に変えて溜め、必要な時には筋肉などで燃焼させて熱を生産します。更にその熱を静脈にのせて心臓に集め、そこから身体全体に暖かな血液を循環させ身体が冷えないようにしています。なんと身体のエネルギー消費量の75%が体温維持に使われているようです。身体の中心は37度ぐらいが適温ですが、手足は心臓から離れているのでそれよりも低いのが基本です。特別に暑い時以外は、外気は体温よりも低い温度なので、通常は身体から熱を放出している状態です。何もしないで裸でいる時に暑くも寒くもない気温は29度(中性温度といいます)と報告されていますが、この温度が最もエネルギーの消費が少ない温度と言えるかもしれません。(起きている時に最適と感じる温度は、服を着て多少は動いているのでもう少し低い温度です)
 ■寒い時には熱の放出が多くなるので、どんどん熱を産出しなければなりません。そのためには食べて熱の元(エネルギー)を作ることも大切ですが、食べるだけでなく、そのエネルギーを使って筋肉を動かして、熱を作り出す必要があります。寒〜い中でもスポーツしている時にTシャツ1枚でも我慢できるのは、筋肉がしっかり熱を作り出しているからですよね。薄着で運動をするという事は、その動作をするためのエネルギーを消費するだけでなく、身体全体を温める熱を作り出すために、エネルギーを消費するということでもあります。サウナの中でじっとしているのは、身体が温められて循環は良くなりますが、熱の産生量は少なくてすむので、痩せる効果は運動とは比べものになりません。
■寒い時には熱の放出が多くなるので、どんどん熱を産出しなければなりません。そのためには食べて熱の元(エネルギー)を作ることも大切ですが、食べるだけでなく、そのエネルギーを使って筋肉を動かして、熱を作り出す必要があります。寒〜い中でもスポーツしている時にTシャツ1枚でも我慢できるのは、筋肉がしっかり熱を作り出しているからですよね。薄着で運動をするという事は、その動作をするためのエネルギーを消費するだけでなく、身体全体を温める熱を作り出すために、エネルギーを消費するということでもあります。サウナの中でじっとしているのは、身体が温められて循環は良くなりますが、熱の産生量は少なくてすむので、痩せる効果は運動とは比べものになりません。  ■ところで、寒さを感じた時には、身体にどんな変化があるのでしょうか。寒ければ寒いほど沢山の熱が奪われますので、寒い状態が長く続くと熱の産生が間に合わなくなり、そうなると心臓や頭まで冷えてしまいますが、それは生命の危機に陥いることになります。だから、そんな事にならないよう、寒いと感じるといち早く交感神経が働いて動脈の血管を閉め、皮膚など末端に流れる血液を最小限にして熱が放出されるのを減らし、暖かな血液が減らないようにして心臓や脳を守ります。寒いと感じたら毛穴を閉めて“トリハダ”になる場合がありますが、これは寒い時に毛を逆立てて毛の中の空気が逃げないようにするという野生の名残らしいです。寒いと身体が震えますが“震える”というのも寒さを防ぐ行動の一つで、筋肉を使って熱を作りだす運動の一つです。冒頭の
「やせポッチ犬が、冬は身体を震わして熱を作るので太らない」というのはそういうことなのです。
■ところで、寒さを感じた時には、身体にどんな変化があるのでしょうか。寒ければ寒いほど沢山の熱が奪われますので、寒い状態が長く続くと熱の産生が間に合わなくなり、そうなると心臓や頭まで冷えてしまいますが、それは生命の危機に陥いることになります。だから、そんな事にならないよう、寒いと感じるといち早く交感神経が働いて動脈の血管を閉め、皮膚など末端に流れる血液を最小限にして熱が放出されるのを減らし、暖かな血液が減らないようにして心臓や脳を守ります。寒いと感じたら毛穴を閉めて“トリハダ”になる場合がありますが、これは寒い時に毛を逆立てて毛の中の空気が逃げないようにするという野生の名残らしいです。寒いと身体が震えますが“震える”というのも寒さを防ぐ行動の一つで、筋肉を使って熱を作りだす運動の一つです。冒頭の
「やせポッチ犬が、冬は身体を震わして熱を作るので太らない」というのはそういうことなのです。 ■それでは寒い所にずっといるとダイエットになって良い、ということなのでしょうか? 身体全体のことを考えると、それは違います。寒い所にずっといるということは、交感神経優位状態なので、血管がギュッと収縮している状態です。言うまでも無く血圧の高い方には非常に危険な状態です。成人病が気になる熟年以降の方にはお勧め出来ないです。また、少しでも身体から熱が逃げないように本能的に背中が丸まって縮こまろうとしますので、姿勢も悪くなり、行動力もにぶってしまいます。
 ■結局、身体のためには必要以上に部屋を暖めず、かといって寒いと感じない温度で過ごすのが良いようです。事務仕事のような軽い動作時は20〜23度程度、冷たい空気は下に溜まるので足下だけが冷える場合は、レッグウォーマーやヒーターなどで温めるのも良いでしょう。冬場の就寝時の室温は16〜19度(夏場は26〜28度)、布団の中は32〜34度が最も良く眠れるようです。手足が冷えて寝つけない方は、就寝直前に手足をお湯などで軽く温め、布団の中も事前にアンカや電気毛布などで32〜34度に温めておくと寝つきが良いです。ただし、一晩中つけっぱなしだと目が覚めやすくなるので、床についた時、電気毛布は最弱程度に調整し、電気あんかも眠りについたらタイマーなどで切れるようにセットすると、良い睡眠に繋がるようです。
■結局、身体のためには必要以上に部屋を暖めず、かといって寒いと感じない温度で過ごすのが良いようです。事務仕事のような軽い動作時は20〜23度程度、冷たい空気は下に溜まるので足下だけが冷える場合は、レッグウォーマーやヒーターなどで温めるのも良いでしょう。冬場の就寝時の室温は16〜19度(夏場は26〜28度)、布団の中は32〜34度が最も良く眠れるようです。手足が冷えて寝つけない方は、就寝直前に手足をお湯などで軽く温め、布団の中も事前にアンカや電気毛布などで32〜34度に温めておくと寝つきが良いです。ただし、一晩中つけっぱなしだと目が覚めやすくなるので、床についた時、電気毛布は最弱程度に調整し、電気あんかも眠りについたらタイマーなどで切れるようにセットすると、良い睡眠に繋がるようです。  ■それから、日頃から運動をして筋肉を養い、効率良く熱を作り出せる身体にしておくことも大切です。なお、急激な温度変化は心臓に良くないので、寒い場所で運動する場合は、ウォーミングアップをしながら少しづつ衣服を調整して下さいね。
■それから、日頃から運動をして筋肉を養い、効率良く熱を作り出せる身体にしておくことも大切です。なお、急激な温度変化は心臓に良くないので、寒い場所で運動する場合は、ウォーミングアップをしながら少しづつ衣服を調整して下さいね。