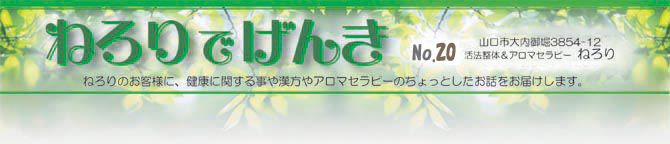
 ■草木が新芽を吹く季節は『肝』の気が旺盛です。東洋医学の『肝』には肝臓という臓器だけでなく、血液(特にその質)という意味も含みます。豊かな血液を身体の末端まで巡らせている状態を、木々が水と養分を吸って枝の先まで行き渡らせる様子で表現し、最も勢いよく成長する春は『肝』が最も働く季節としています。
■草木が新芽を吹く季節は『肝』の気が旺盛です。東洋医学の『肝』には肝臓という臓器だけでなく、血液(特にその質)という意味も含みます。豊かな血液を身体の末端まで巡らせている状態を、木々が水と養分を吸って枝の先まで行き渡らせる様子で表現し、最も勢いよく成長する春は『肝』が最も働く季節としています。■さて、肝臓という臓器、とっても大切な臓器という事はどなたでもご存知です。では「どんな仕事をしているのでしょうか?」という問に、「お酒を飲む時に大切な部位!!」って声だけが聞こえてきたりして……。医療関係の方には解りきったお話かとは思いますが、簡単に肝臓の役割をまとめてみました。
肝臓は、腸で吸収された様々な栄養素を分解して身体に利用できる形に変えます。そして必要な栄養素は血液中に流し、いらない物はおしっことして身体の外に出すように仕分けします。直ぐに必要が無い糖や脂質、タンパク質(脂肪として)を貯蔵し、必要に応じてこれらを分解して生命活動に必要なエネルギーを産生しています(肝臓に溜めすぎると『脂肪肝』になります)。余分な栄養分は肝臓以外にも身体の脂肪細胞が蓄えます(これが内蔵脂肪や皮下脂肪ですね〜)。また、身体にとって毒となる物を分解して処理する働きもあります(お酒の分解もこの作用の一つです)。
「血液」と聞くとまず心臓を思い出す方が多いですが、心臓は“血の流れ”を司り、肝臓は“血の内容”に大きく関わっています。ですので、肝臓の機能が落ちると動くためのエネルギーが充分に供給されなくなるので、身体がとってもだるくなります。また、脳にもエネルギーが必要ですが、これも足りなくなるので、反応がにぶくなったり、充分に物事が考えられなくなったりします。身体を再生したり、整えたりする栄養素も充分に行き渡らなくなるので、肩こりなどの“凝り”や筋肉痛も起こしやすくなります。また、解毒や選別の力も落ちるので、血液中に身体に悪い影響を及ぼす物が混じり、湿疹や肌荒れも起こしやすくなります。
 ■ところで、バイタリティ溢れる方の事を「血の気が濃い人」と言いますが、正にこれは『肝』の気がとても旺盛な方を表現した言葉です。肉類が大好きで食欲旺盛、貧血なんてあり得ない濃い血の方、いつもエネルギッシュに活動し、お酒も強かったり……いつも肝臓パワー全開状態の方です。このタイプの方の性格は、情緒豊かで精力的に仕事をこなすけど、気が短いのが“玉にきず”。
■ところで、バイタリティ溢れる方の事を「血の気が濃い人」と言いますが、正にこれは『肝』の気がとても旺盛な方を表現した言葉です。肉類が大好きで食欲旺盛、貧血なんてあり得ない濃い血の方、いつもエネルギッシュに活動し、お酒も強かったり……いつも肝臓パワー全開状態の方です。このタイプの方の性格は、情緒豊かで精力的に仕事をこなすけど、気が短いのが“玉にきず”。興奮する事を「気が高ぶる」と言いますが、これは余分な気が頭に上がってしまった状態を表現した言葉です。「血の気が濃い人」はエネルギーの取り過ぎで(食べ過ぎ・飲み過ぎで)余分な気を蓄えがちなので、その気が頭に溜まり気が高ぶりやすくなります。だから「血の気が濃い人」は「気が短く」なります。

しかし、肝臓の機能も年齢とともに衰えていきますので、いつまでも若い時と同じ生活をしていると、旺盛な状態からオーバーヒート状態になり、壊れてしまいます。そうなるとエネルギッシュな良い部分が減ってきて、ただただ怒りっぽい人になっていきます。以前に増して激昂しやすくなった、いつもイライラしているなどは『肝』がオーバーヒートしているかもしれません。『肝』の気が旺盛な方は過信せずに、年齢に応じて『肝』をいたわって下さい。特に肝臓に脂肪が溜まった『脂肪肝』は、肝臓の働ける部分が減ってしまった状態なので、とっても肝臓に負担が掛かります。
■最後に『肝』のいたわり方の一例をあげてみました。
-
 ●食べ過ぎ・飲み過ぎ。脂っこい物や甘い物、お酒は言うまでも無く、タンパク質の取り過ぎに注意。タンパク質(アミノ酸類)の分解・排泄は肝臓だけでなく腎臓の負担も大きいです。
●食べ過ぎ・飲み過ぎ。脂っこい物や甘い物、お酒は言うまでも無く、タンパク質の取り過ぎに注意。タンパク質(アミノ酸類)の分解・排泄は肝臓だけでなく腎臓の負担も大きいです。 - ●タンパク質不足も脂肪肝のもと。肝臓に蓄えられた脂肪を利用する時にはタンパク質を必要としますが、これが不足すると脂肪が利用できずに肝臓に溜まってしまいます。良質のタンパク質を適度にとりましょう。大豆食品はお奨めです。
- ●サプリメントの多量摂取で肝臓の分解・解毒作用がフル回転、なんでも適度が大切です。特に薬は自己判断で多種を飲み続けるなんてもってのほか、お医者さんに相談しましょうね。
- ●ストレスを溜めないこと。そして睡眠と適度な運動。 以上の4点、どの病気にも共通する普通のお話ですよね。
 ◆「春眠暁を覚えず」という故事かありますが、春はなんとなく眠たい季節です。就寝中に気持ち良く眠れるのなら良いのですが、目覚めていても身体がだるい・眠いなどの症状があるとちょっと困りものです。もしかして、身体が未だ“冬眠”から覚めてないのかもしれません。
◆「春眠暁を覚えず」という故事かありますが、春はなんとなく眠たい季節です。就寝中に気持ち良く眠れるのなら良いのですが、目覚めていても身体がだるい・眠いなどの症状があるとちょっと困りものです。もしかして、身体が未だ“冬眠”から覚めてないのかもしれません。◆食料の乏しい冬、自然の動物は出来るだけ活動を抑え体内のエネルギーの消費を節約して生活しています。そして春になると一気に活動を開始します。人間も、衣類や暖房を使って快適に暮らしているとはいえ、やはり光や気温・気候に応じて自律神経が体内を調整しています。この自律神経が、気候・気温の大きな変化についていけないと、だるさや眠気というかたちで出てしまいます。
 例えば、睡眠を誘う脳内の物質(メラトニン)は、暗さを感じると分泌を始め、自律神経に働きかけて身体をお休みモードにしていきます。春になって日が長くなっているのに、それを感じない生活をしていると、メラトニンの分泌がいつまでも冬のパターンを引きずり、自律神経の調子を狂わしてしまいます。
例えば、睡眠を誘う脳内の物質(メラトニン)は、暗さを感じると分泌を始め、自律神経に働きかけて身体をお休みモードにしていきます。春になって日が長くなっているのに、それを感じない生活をしていると、メラトニンの分泌がいつまでも冬のパターンを引きずり、自律神経の調子を狂わしてしまいます。“冬眠”から身体を目覚めさせるために、朝起きたら真っ先にカーテンを開けて朝日を浴びましょう。室内でも良いですので、日中も春の日差しを感じられる生活を心掛けましょう。すると身体を目覚めさせ活動させる脳内の物質(セロトニン)の分泌が促され、自律神経の調子も整います。
◆次に、目覚め物質・セロトニンには、重力に逆らう筋肉(抗重力筋)の働きを促す力があります。ですので、寒い時に暖房の前でヌクヌクしていた方は、立ち上がって軽い体操をしてみましょう。そうするとセロトニンの分泌が促進されますので、動く事が段々と楽になりますよ。なお、セロトニンは脳以外に腸でも沢山分泌されていますので、お腹の調子を整える事も大切ですが、適度な運動はそれにもとっても有効です。特に春に吹き出物が出やすい方は、腸の働きが弱っている可能性が高いですので、ラジオ体操など軽い体操をお奨めします。
◆それから、身体が春型になって活発に活動し始めると、それに見合ったエネルギーや酸素が必要となります。炭水化物や脂質をエネルギーに変えるビタミンB1(豚肉・大豆などの豆類など)・B2(レバー・卵黄・牛乳など)、タンパク質の代謝や中枢神経の働きを整えるビタミンB6(レバー・魚の赤身・ごまなど)、酸素を運ぶ赤血球の生成を促進するビタミンB12(レバー・あさりなどの貝類・海藻類など)をしっかり取りましょう。
◆アロマオイル(精油)で頭をすっきりさせるには、ローズマリーやペパーミント、レモンがよく使われます。
 ローズマリーには血流を高める作用があり脳の活性化にもよいです。ただし、血圧の高い方にはお勧めしません。ペバーミントは、カフェインのように中枢神経を興奮させる働きがあり、目覚めをすっきりさせてくれます。でも妊婦さんや小さいお子さんは控えて下さいね。また、多くの柑橘類の皮はリモネンという成分を多く含み、交感神経を活性化する効果があります(注)。柑橘類の精油は皮から搾るので、果肉以上にその効果は期待できます。頭がポーッとする時には、レモンがお勧めで、こちらは特に禁忌はありませんのでどなたでも使えます。(注:レモンは副交感神経に働く成分も含み、レモンの精油の作用としては降圧に働きます。)
ローズマリーには血流を高める作用があり脳の活性化にもよいです。ただし、血圧の高い方にはお勧めしません。ペバーミントは、カフェインのように中枢神経を興奮させる働きがあり、目覚めをすっきりさせてくれます。でも妊婦さんや小さいお子さんは控えて下さいね。また、多くの柑橘類の皮はリモネンという成分を多く含み、交感神経を活性化する効果があります(注)。柑橘類の精油は皮から搾るので、果肉以上にその効果は期待できます。頭がポーッとする時には、レモンがお勧めで、こちらは特に禁忌はありませんのでどなたでも使えます。(注:レモンは副交感神経に働く成分も含み、レモンの精油の作用としては降圧に働きます。) 退屈した時・疲れた時や眠たい時・寝起きなどに出るあくび、猫や犬もあくびをしますが、なんと鳥や爬虫類もあくびをするそうです。なぜあくびが出るのかは様々な説がありますが、実のところはまだよく解っていません。眠たい時に頭を覚醒させるためとか、緊張をほぐすために出るとか言われています。
退屈した時・疲れた時や眠たい時・寝起きなどに出るあくび、猫や犬もあくびをしますが、なんと鳥や爬虫類もあくびをするそうです。なぜあくびが出るのかは様々な説がありますが、実のところはまだよく解っていません。眠たい時に頭を覚醒させるためとか、緊張をほぐすために出るとか言われています。仕事などで緊張が極限状態の時に「ぷぁっ」とあくびが出て「こんな時にあくびなんて!」って焦ったり叱られたりした事はありませんか? 無理にこらえて、鼻がプワッと膨らむのもイヤですね。あくびをこらえるのに『舌を前歯の裏側に押しつける』という方法がありますのでお試し下さい。
 ところであくびは伝染する事がありますが、それは人や猿など感情を持った動物だけのようです。そして、赤の他人よりも身近な人や同じ状況にある人など、気持ちが通じ合う人の間で伝染するようです。もし、貴方が愛犬の前であくびをして、ワンちゃんにあくびがうつったとしたら、貴方とワンちゃんは気持ちがしっかり通じ合っているのかもしれませんね。
!
ところであくびは伝染する事がありますが、それは人や猿など感情を持った動物だけのようです。そして、赤の他人よりも身近な人や同じ状況にある人など、気持ちが通じ合う人の間で伝染するようです。もし、貴方が愛犬の前であくびをして、ワンちゃんにあくびがうつったとしたら、貴方とワンちゃんは気持ちがしっかり通じ合っているのかもしれませんね。
!