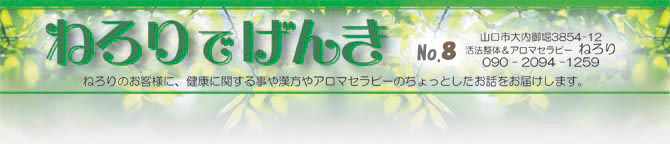 |
||
|
||
| 東洋医学の考えでは、「金」には「変革、清める」などの意味があります『金は従革と日う』。「肺」の気の最も大切な仕事は、体内の古い空気を新しい空気に変えていくことです。それは身体を清めることに繋がります。それから、身体から不要な物を出すのには「大腸」も重要です。「肺」と「大腸」は、一見あまり関係が深く無いようですが、東洋医学では身体から古い物を出し清めていく働きの臓腑として、表裏の関係に置いています(裏面の五行表参照)。秋は「大腸」の気も旺盛なので、旬の食材をしっかり食べて不要な物を出し、身体をリセットして下さい。 | ||
|
||
| 東洋医学の「肺」は、皮膚の呼吸・調整機能も含めます。皮膚は暑い時は汗を出して身体を冷やしたり、寒い時は毛穴を締めて熱が逃げないようにしたり、「外邪」が身体に入らないように調整しています。この皮膚の調整機能を超えた時に風邪をひいてしまいます。逆に乾布摩擦などで皮膚を強くしたら風邪をひきにくくなったり、喘息が治まったりしますよね。 これから空気が乾燥する季節になりますので、風邪で「肺」の気に負担をかけないようにお過ごし下さい。 |
||
|
||
| 化粧水の基本の作り方は、日本酒30mlにアロエのしぼり汁5mlを入れて混ぜるだけ。冷蔵庫に入れて1〜2週間で使いきって下さい。 作り方の一つをご紹介します。柚子の種を煮沸した保存瓶に入れ、種の高さの3倍になるぐらいまで純米酒または20度程度の焼酎を注いで下さい。常温に置いて1日ごとに軽く振ると2週間ほどでとろみが出てきます。この時点でも使えるのですが、1ヶ月ほど置くと種内部の成分もしっかり出るようです。これをガーゼでこし、冷蔵庫で保存して使って下さい。少し強いと感じた場合は、蒸留水で2〜3倍に薄めてみて下さい。敏感肌の方はパッチテストをして下さいね。 |
||
|
||
| 疲れたなぁと感じた時には、「肺の気」の出入り口である鼻から息をぐぅっと吸ってお腹をふくらませ、今度は口から出来るだけ長〜く息を吐き出して下さい。腹式呼吸を普段していない方は、上手にできなかったりしますが、続けているうちに深い息できるようになります。おへその下あたりに手を軽く置いて、お腹の動きに意識しながらしてみましょう。私も、仕事の合間に調息と言って、目をつむり、新しい「気」を身体に取り込むイメージで腹式呼吸をし、身体をリセットしています。 秋の美味しい空気を胸いっぱいに……胸だけでなくてお腹にもいっぱい取り込むイメージで深呼吸をして下さいね。 |
||
「表裏の関係」とは |
||
| 東洋医学では食物、体質、病気など、様々な事柄を4種の見方で各々2つに分けます(八綱弁証)。それは「陰・陽」「寒・熱」「虚・実」そして「裏・表」。どちらにも偏らない状態は「中庸」と言います。 病気の状態を表す時の「表裏」は、東洋医学を勉強されたお医者さんや薬局では必ずそれを診断して漢方薬を処方します。まだ病気が表面的で軽い状態を「表証」、内臓まで達しているような重い状態を「裏証」と表現します。 臓腑も「表裏」に分ける事があります。五行表の五臓が「裏」六腑が「表」です。そして、表の縦は、関係が深いとされる臓腑です。今回、肺と大腸の関係は表面に簡単な文章を書きましたが、心と小腸の関係は今度書きます。肝・胆、胃・脾(膵のこと)、腎・膀胱はなんとなく理解できるかと思います。 身体の異常は「六腑」の方に出てきやすく、こちらは比較的直りやすいので「表」、五臓の方は、異常が出にくく、出ると簡単には直らないので「裏」という考えです。表の中に「三焦」「心包」という聞き慣れない臓腑がありますが、簡単に書くと「三焦」とは消化器系統や水分を調整するもの、「心包」は循環器系統を調整するもので、東洋医学独特の考えの臓腑です。 |
||



